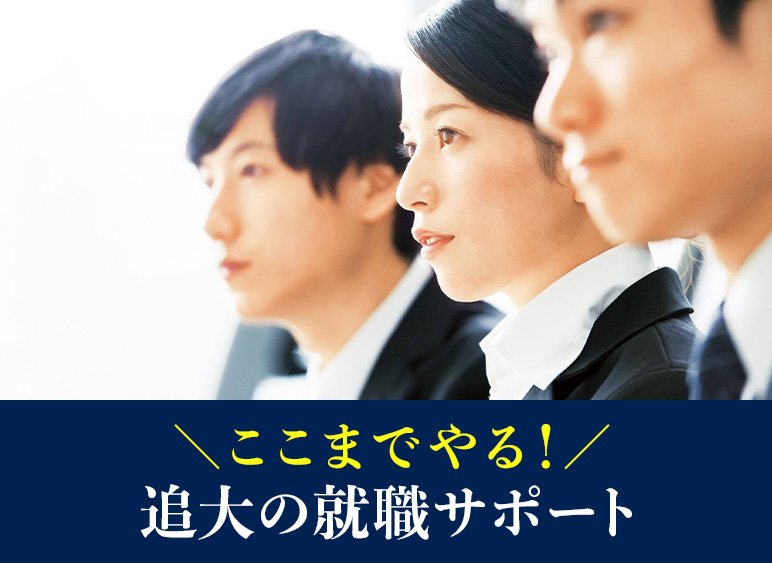学部案内


気になる知財の疑問を解決!
「◯◯は✕✕に似すぎ!パクリ」って言われてるけど著作権侵害? 二次創作の著作権はどうなってるの? AIを利用するとき何に気をつければいい?……など、日常誰もが使うSNSや動画共有サイトで浮かび上がる疑問には、知的財産法の体系を学べば、しっかりと根拠を持って答えられるようになります。

私のバイト先ってブラックなん?
企業が労働者を働かせる際には守るべき基準が法律で定められています。労働法の講義で労働時間や休憩、休日、賃金などの基準の内容を学ぶことにより、自分のバイト先がブラックがどうか理解することができるようになります。

会社ガバナンスの法制度を学ぼう
企業不祥事を未然に防止し、健全な企業経営を実現するにはどのような内部体制が望ましいか、商法・会社法の講義で日本の法制度のみならず、諸外国の企業に関する法制度の学びも通じて、会社ガバナンスの法制度を一緒に学ぼう
令和の市民視点で法律を考える、
新しいスタイルの法学を展開。
法に関する専門知識および法知識の基礎となる基本事項や思考方法といった法的素養とともに、幅広く深い教養、主体的な判断力や豊かな人間性を身につけます。それらを社会のさまざまな場面に適用できる応用力をもって、社会のさまざまな分野で日常的に生じる法的な業務や諸問題を的確に処理することのできる職業人を育成します。
学びの領域Territory
養成する具体的な人材像に対応した2つのコース。
1年次からの主体的な学びでつちかった視点・関心を、目指す人材像に合ったコースに分かれて、さらに展開、探求する。
-
政策法務コース
-
主に公務員を目指す
主として、国家公務員(総合職・一般職)・地方上級公務員やNPOなどの政策法務を目指すコースです。行政法、地方自治法などの知識をもとに、行政実務に携わり、政策立案(産業推進、都市計画、雇用対策、福祉充実など)ができる力を養成します。
法的素養を有した職業人へ
- 進路
イメージ -
- 自治体職員(行政事務、警察官、消防職員)
- 裁判所・検察事務官
- 国家公務員(行政事務)
- 法科大学院などへの進学
- 進路
-
企業法務コース
-
主に民間企業への就職を目指す
主として、民間企業へ就職し企業法務を目指すコースです。民法・商法に加え、経済法や労働法などの法的知識も活かし、商取引関係や労務関係などの企業活動における法律事務の処理や法律問題(M&A、訴訟対策、企業再生など)に対応する力を養成します。
法的素養を有した職業人へ
- 進路
イメージ -
- 上場・大手企業
- 金融機関
- 司法書士・行政書士
- 法科大学院などへの進学
- 進路
学びの特色Features
ジェンダーや国際関係、企業法務など、
現代のニーズに応える課題を扱う。主に法律家を目指すこれまでの法学部とは一線を画す、市民目線の法学部を目指しています。オーソドックスな従来のカリキュラムは残しつつ、抽象的な法律の項目だけを学ぶのではなく、個人にとって身近で誰にとっても大切なテーマや、現代社会のニーズに沿った課題も積極的に扱っていきます。例えば次のような課題です。
科目例
- 消費者法 消費者問題の法的解決法を考える
- 企業倫理と企業法務 企業のあり方と未来を考える
- 国際取引法 国際的な商取引の仕組みを知る
- ジェンダーと法 ジェンダーの視点を明らかにする
- 科学技術と法 先端技術への法の対応を考える
グループ学習をはじめ、
学生参加型の主体的な学びを展開。1年次から少人数のゼミ形式の授業を展開。従来の大講義形式だけでなくグループ学習を取り入れ、学生同士が語り合い討論する主体的な学びを重視しています。
-
1年次
法学文献を演習形式で講読し、
法学の基本的な概念や思考様式を身につける -
2年次
法学に関わる情報収集や分析・評価の方法を
演習形式で身につける -
3年次
各自が専門領域を絞り、基本的な調査・研究を行う
-
4年次
実社会の課題なども取り上げ、
複眼的な観点から調査・研究を行ってまとめあげる
-
キャリアサポート (全学向けに正課外で展開しているプログラムです)Career Support
授業とあわせて相乗効果を狙う
課外学習による多様なキャリア支援公務員試験や各種資格試験で理解が問われる法律系科目については、法学の思考様式の礎となる基礎法学を踏まえたうえで、必須となる憲法・民法・行政法を学ぶことができます。各分野における第一人者の教授陣による授業から法律や政策の専門知識を学び、ゼミ形式の授業で、公務員試験の2次試験や就職活動で必要となるプレゼンテーション能力や論文作成能力を身につけます。
さらに法学部では、オンライン学習ツール (TKC 公務員試験学習ツール) の活用、法学検定試験や自治体法務検定を利用した学習、キャリア支援のための学部主催講演会の開催、学生の自主的な課外学習活動の支援など、さまざまな形で学生の勉学のサポート体制を整えています。授業
-
選べるプログラム
- ● TKC公務員試験学習ツール
- ● 「法学検定試験」「自治体法務検定」への取り組み
- ● 学生の自主的な課外学習活動の支援
- ● キャリア支援のための法学部主催講演会
資格等取得奨励金制度
資格取得した学生に奨励金を給付しています。追大は挑戦する学生を経済的な面からも応援します(※規定あり)。
対象資格と奨励金額の一例
-
国家公務員[総合職]ほか
同等レベルの公務員試験 200,000円 -
地方上級公務員
【都道府県庁/政令指定都市・特別区】
ほか同等レベルの公務員試験 100,000円
Pick up 科目Pick up Subject
- 刑事手続法Ⅰ
-
刑事手続法(刑事訴訟法)の基本原理を修得し、その手続きの前半にあたる「捜査法」の分野を中心に授業を行います。職務質問・所持品検査などの任意捜査、逮捕・勾留・捜索差押えなどの強制捜査に関して理解します。
- 法学入門
-
基礎法学(法哲学、法社会学、法制史など)の基本的な思考様式と方法をもとに、実定法学(憲法、民法、刑法、行政法、商法)の初歩を学べる授業を実施。法の体系と基本的な考え方を理解し、初歩的な法解釈の方法を身につけます。
- 比較法
-
日本を含むさまざまな時代・国・地域の法のあり方を比較検討します。ドイツとアメリカの憲法を比較して日本国憲法を考えるといった授業などを通じて法の多様性への視座を身につけ、日本の法制度の独自性を理解することを目指します。
- 国際関係法Ⅰ
-
各種国際法が確立されるに至った事例を取り上げ、地理、歴史、経済に関する知識を活用し、それらがどのように法的な対立を生んだかを考察。ローマ法までさかのぼることも多い国際法の原則を理解し、現代の国際課題の解決へと役立てます。
- 知的財産法
-
知的財産法に関する基礎的な知識の修得を目指し、知的財産法を構成する特許法、著作権法、意匠法、商標法などについて理解します。身近に実際に生じる知的財産法に関する基本的な問題を実践的に解決できる能力を養います。
取得できる資格Licence
● 学芸員
● 社会教育主事(※卒業後、1年以上社会教育主事補を務めた後に取得)
取得を目指す資格
● 宅地建物取引士
● 行政書士
● 司法書士
合格を目指せる試験
● 国家・地方公務員試験
● 法科大学院入試
● 司法書士・行政書士試験
● 法学検定試験
● 宅建試験
● ビジネス実務法務検定試験®
学部長メッセージMessage
-
追手門学院大学 法学部での
新しい学びと切り開かれる未来 -

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。法学部長の高田篤です。皆さんが追手門学院大学法学部の一員となり、新たな学びの第一歩を踏み出されることを、心から嬉しく思います。
本学法学部は2023年に設立され、今年で3年目を迎えます。先輩たちは、ゼロから学びや学生生活を築き上げ、法学部の環境を整え、伝統をつくりつつあります。そして今日からは、皆さんがその流れを受け継ぎ、新たな歴史を刻む番です。
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。法学部長の高田篤です。皆さんが追手門学院大学法学部の一員となり、新たな学びの第一歩を踏み出されることを、心から嬉しく思います。
本学法学部は2023年に設立され、今年で3年目を迎えます。先輩たちは、ゼロから学びや学生生活を築き上げ、法学部の環境を整え、伝統をつくりつつあります。そして今日からは、皆さんがその流れを受け継ぎ、新たな歴史を刻む番です。
1 法学部での学び
大学での学びは、高校までとは大きく異なります。ただ知識を覚えるだけでなく、社会や世界の変化を捉え、それに対応できる力を養うことが求められます。法学の特徴は、憲法・民法・刑法など多様な法分野の具体的な問題を学ぶことが、そのまま法体系全体の理解へとつながる点にあります。その過程で、個別の事象を深く分析する力と、全体を見渡し体系的に考える力の両方が鍛えられます。
また、法は時代とともに変化するものです。今日の常識が明日には変わることも数多くあります。そのため、単に現行の法を知るだけでなく、「なぜその法が重要なのか」「どのように変化してきたのか、今後どう変わるのか」といった、客観的かつ相対的な視点を持つことが重要です。
こうした力を養うため、本学法学部では、大講義だけでなく、1年生から4年生まで各学年に応じた少人数制の「ゼミ」を設けています。先生や仲間と議論しながら学ぶことで、実践的で総合的な思考力を養うことができます。こうした充実した少人数教育を提供する法学部は多くはありません。本法学部で培った実践的で総合的な思考力は、卒業後も社会で活かせる、一生ものの財産となるでしょう。
2 課外での学びと目標の達成
大学での学びは、一生ものの知的基盤を築くことに加え、具体的な目標達成の手段としても重要です。例えば、司法試験、公務員試験、各種資格試験を目指す人にとって、受験勉強は不可欠です。本学では、講義・ゼミに加え、課外での学習機会も豊富に用意しています。本日のオリエンテーションでも詳しく紹介されるので、ぜひ活用してください。
その際、特に難しい試験の合格には、学部で培う思考力も不可欠だということを忘れないでください。また、試験の合格は大きな成果ですが、そこがゴールではありません。合格後にどのように社会で活躍するかが肝心です。そのとき、皆さんを支えるのは、学部で培った思考力や経験です。試験合格に向けた勉強だけではなく、長期的な視野を持って、さまざまなことに積極的に取り組んでください。
3 学部の「伝統」と自分自身を形作る
本学法学部はまだ若く、伝統を築いている最中です。先輩たちは、ゼロから挑戦し、成果を積み上げてきました。しかし、伝統はまだ完成されていません。
皆さんは「3期生」として、この新しい法学部の歴史をさらに発展させる役割を担っています。これは、他の歴史ある法学部にはない、自由に新しい文化を創り出せる貴重な機会です。そして、授業、課外活動、さまざまな場面で主体的に行動し、充実した学生生活を送りながら、自分自身を形作ってください。
おわりに
大学生活では、学問だけでなく、多くの新しい出会いや経験が待っています。時には困難に直面することもあるでしょう。しかし、それを乗り越えることでこそ、成長が生まれます。私たち教員は、皆さんの挑戦を全力でサポートし、ともに歩んでいきます。
3年目を迎えた本学法学部は、皆さんとともにさらに発展していくことでしょう。新しい環境の中で多くを学び、充実した大学生活を送ってください。皆さんの成長と活躍を心から楽しみにしています。
(2025年4月1日 新入生オリエンテーションでの学部長挨拶)
教員インタビューInterview
-
グループ学習など主体的な学びを取り入れ、
市民目線で法律を考える新しいスタイルの法学部に -

三成 美保 教授
専門分野:法制史、ジェンダー法学本学に設置したのは、これまでの法律家を目指す法学部とは一線を画す、市民目線の法学部です。オーソドックスな従来のカリキュラムは残しつつ、抽象的な法律の項目だけを学ぶのではなく、身近なテーマであるジェンダー法学やLGBT、選択的夫婦別姓など、現代社会のニーズに沿った課題についても積極的に扱っていきます。例えばDVやハラスメントなどの問題に直面した際、法律を知っているかどうかで情報へのアクセスの仕方が変わってきます。男女の問題や家族の問題とはいえ、そこには何かしらの法律が存在しているのです。また、SDGsなどの国際的な課題における日本の法整備は十分なのか、グローバル規模で考えた法律や権利の位置づけなど、文化や歴史を他国と比較して考えてみるとさらに興味深い学びになります。授業スタイルについては、従来の大講義形式だけでなくグループ学習を取り入れ、学生同士が語り合い討論する主体的な学びを進めます。単に情報を集めるだけではなく、分かりやすく要点をまとめて発表するなど、学生同士の学び合いの中にこそ新たな発見があるはずです。